
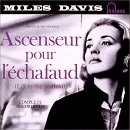
Vの音楽史
by veneno
ジャケットをクリックでアルバム詳細が見れます。
(1)全ての始まりに
旧豪族の豊かな家庭に生まれた女性が、片親に育てられた貧しい三兄弟の次男坊に嫁いだ所から私の家庭は始まります。病院を営んでいた叔父の「あいつは大物になる」の一言で結婚してしまった無鉄砲な女性が私の母親です。私の音楽遍歴には、彼女の影響が色濃く出ています。
音楽、その夜明け前
鳥のさえずりや虫の音、そして風の音が好きでした。TVにあまり興味の無い子供と思われていたようです。実を言うと私は動物や鳥と話が出来たので(笑)彼等から教えられたのです、「君の求めている物は、そこには無いんだよ」と。虚構の世界に惹かれる自分と現実を掴もうとする自分の葛藤が、すでにこの頃から始まっていました。自分の中にいるもう一人の自分が、どれだけはしゃいでもそれを冷静に見ているという感覚です。自分の中の自分が周囲と関わり合うのを拒否しだすのにそう時間は、かかりませんでした。
TVといえば映画ですね。ミュージカル、マカロニウエスタン・・・あの頃は映画用の素晴らしい音楽が沢山ありました。音楽とイメージをリンクさせるクセは、この頃ついたのだと思います。S&Gもマイルス・デイビスも映画音楽の人でした。勿論ラジオには映像が有りませんので、それらの類だと思っていました。この世の中にクラシック以外で、人前で演奏をしてお金を貰う人達が存在するとは考えもしませんでした。
我が家にステレオが来たのは1969年頃だと思います。父親が友人から20枚ほどのLPと一緒に譲り受けたそうです。クラシック、映画音楽、(ホテルのロビーで流れていそうな)ムード音楽のたぐいです。それが原因なのか、まだ音楽に夢中になるというほどではありませんでした。たった1枚だけ有ったThe
4 SeasonsのRag Dollのドーナツ盤も何も知らず何も感じず聴いていました。歌謡曲の存在も知りませんでした。私は音楽に特別な興味がなかったのです。
(2)覚 醒
随分ませた子供だったと思います。身の回りの本を片っ端から読んでいました。子供用の本など殆んど有りませんでしたから理解は出来ていなかったと思いますが父親の医学書から江戸川乱歩まで手を出し、まだ早いと叱られたりもしました。学校の図書館に自由に出入り出来る年になると、ここでも片っ端から読む事になります。いつも何か新しい刺激を求めていたのだと思います。
自分の事を色々と言われる事に嫌悪感が有りました。あなたが考えている様な人間じゃない、といつも考えていました。そのくせ自分を正しく理解して欲しいとも考えていたのです。その為に沢山の絵や文章を書いていました。その評価にも満足しないひねくれた子供だったのです。
1971年の冬(多分1月だったと思います。)TVのニュースか何かでアート・ブレイキー来日というのを見ました。番組中に演奏したのかビデオだったのか覚えが有りませんし1曲演奏したのか途中で終わったのかも覚えが有りません。
演奏を聴かせる、そこには自分の全く知らない世界が有りました。いや、ずっと前から身の回りに存在していたのに鈍感な私は全く気が付いていなかったのです。初めて音楽が音楽として存在する事に気が付いたのです。何の変化も無い田舎に住む鈍感な私にとって絵画や文章以外の感情伝達方法の発見、それはカルチャー・ショック以外の何物でも有りませんでした。
本当にショックでした。音で今の自分を表現しようとする人達がいる!私の体の中に堰をきった様に音楽が流れ込みました。今まで何も感じなかった音楽に体が反応するのです。レコードやラジオから流れる音楽に耳を傾けるようになりました。ジャンルとか一切関係有りませんでした。とにかく何でもいいから音楽を聴きたいと思ったのです。
初めてレコードを買って貰ったのもこの頃だと思います。LPなんて買って貰えません。S&Gのバイ・バイ・ラブ(\400)のシングルでした。今、考えてみれば名前を知っているのであれば別に何でもよかったのかもしれません。自分から求めて音楽を聴くという行為自体に酔い始めていました。
(3)
太陽がぎらぎらと眩しく輝いていた。ぼくは父さんの車の横に立っていた。エンジンを掛けっぱなしの車はブルブルと低い音をたてていた。
まだ舗装のされていない道はずっとずっと真っ直ぐで、その始まりと終わりは森の中に消えている。道の両脇には田んぼが広がっていて、その両端はずっと向こうの森まで続いているように見えた。稲の葉が太陽の光を反射してキラキラと光っていた。車の中の掛けっぱなしのラジオから声が聞こえてくる。男がけたたましく早口で話し女の人が笑う、それの繰り返しだった。ぼくは車の影に隠れるように座り、汗でべとべとになったシャツを両手で掴んでパタパタとおなかや背中に風を送り込んだ。
父さんがぼくに待つように言ってもう随分時間が経つ。ぼくは少し後悔していた。「やっぱり、母さんと家にいればよかった。」小さな声で独り言を言った。車の影から空を見上げると太陽がそこから動くのを止めた様にさっきと同じ場所でぎらぎらと輝いている。時々思い出したように車が通り過ぎるだけで、まるで時間が止まっているようだった。ずっと同じ時間の中でじっとしているような感じがしてきた。
あれっ、ぼくは座ったままで首を回し車の中をみた。ラジオからGilbert
O'SullivanのAlone Againが流れてきた。その次がAmericaのA
Horse With No Nameだった。少し気分が良くなってきた。日差しも心持ち柔らかくなった感じがした。「もう少し、このままでもいいかな」NilssonのWithout
Youを聴きながらそんな気分になりだしていた。涼しい風が僕の顔をくすぐるように吹いていった。稲の葉がさわさわと揺れた。シャツの汗もとうに乾いていた。
父さんが戻ってきたら言おう「少しも退屈じゃなかったよ」って。
(4) BOSS 「引越しの前日」1972
よく晴れた日の午後、ぼくは庭の芝生の上に大の字に寝そべって、青空に浮かぶ雲を見ていた。
手足から背中まで広がる芝生の葉先のチクチクした感じが気持ち良かった。
朽ちかけた垣根の間から流れ込む風が、もうそこまで秋が来ている事を知らせていた。
あした、引越しをする。この家ともさよならだ。
母さんは「そんなに遠くじゃないから」って言ったけど、すぐに他の人が入る事をぼくは知っていた。
父さんにも「今度の家は2階建てで、お前の部屋もある。」って言われたけど、芝生の庭が無いじゃないか、って言いたかった。
ぼくは、この小さな芝生の庭が大好きだ。
体を起こして小屋の方を見るとBOSSが前足の上にあごを乗せたまま、少しだけ目を開いて、こっちを見た。
ぼくよりも1歳年上だからもう随分お爺さんのはずだ。でもそんな感じは全然しない。
きのう一緒に裏山へ遊びに行った時だって、いつもと同じ様にBOSSはぼくの少し前を歩き、ずっと回りを警戒していてくれた。
BOSSは今だって裏山の王様だ。どんな動物もBOSSに歯向かったりしないし、BOSSだって大人しくしていれば何もしやしない。BOSSと一緒なら何も怖いものなんかないんだ。
でも、引越したら散歩も鎖を付けて行かなきゃいけないって父さんが言っていた。
BOSSには鎖も首輪も似合わないのに。無くたって何も悪い事なんてしないのに。
ぼくは少しだけ泣けた。引越しをしてこの家とサヨナラするせいなのか、それとも少しだけ秋を感じさせる風のせいなのか、自分でもよくわからなかった。
「よしっ!」ぼくは靴を履いてBOSSのそばに行った。BOSSはぼくが近くに来るのがわかるとゆっくりと起き上がって体をブルブルッとゆらした。
「BOSS!散歩に行こう!」ぼくは鎖でつながれた首輪を外すと裏山に向かって歩き出した。
BOSSは、頭を上げ胸を凛と張り、ぼくの少し前を歩き出した。
帰ってきたらラジオを持ち出して芝生の上でBOSSと一緒に聴こう。
シカゴが流れるといいな。それからエルトン・ジョンも。